- Topics
特許庁が商標登録を認めた=識別力がある……ではない
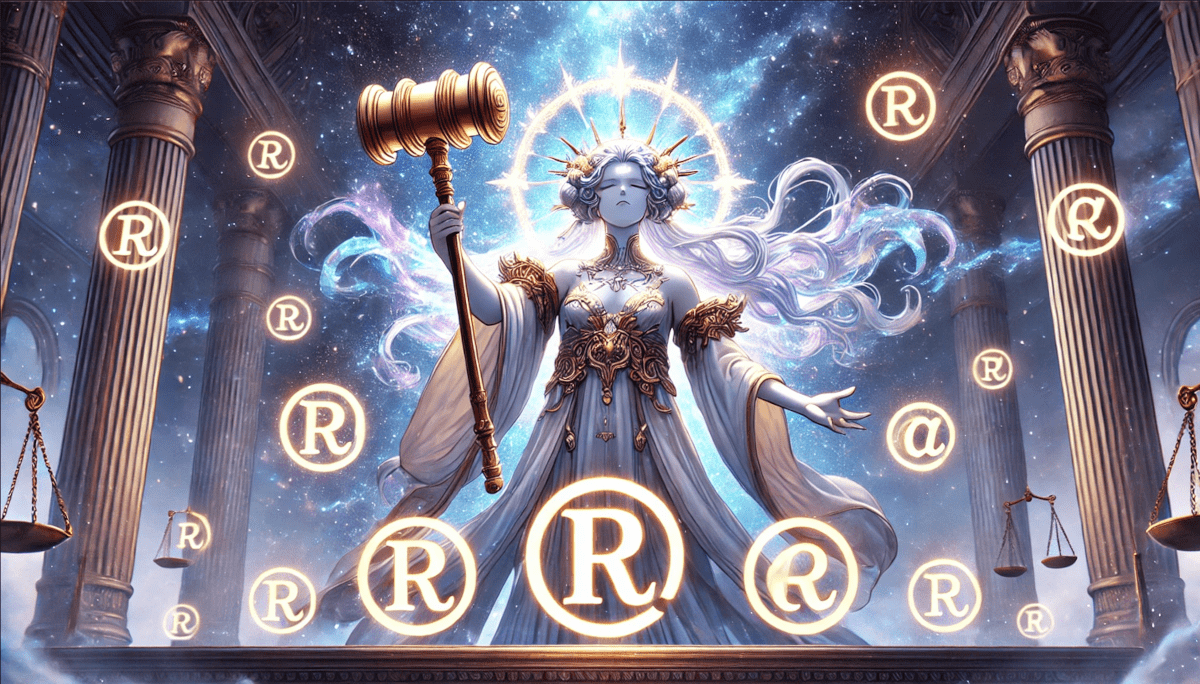
商標登録出願を行い、特許庁から商標登録査定を受けたと聞くと、「自分の商標は識別力が十分にあるから登録されたのだろう」とつい考えがちである。
ほとんどの場合、大間違いだ。

小久保
実際、弁理士までもが「商標登録された。つまり、識別力が認められた!」とか言っちゃうんだよね。。。
もちろん、ある程度の「識別力」がなければ登録は認められないのだけど、実際には「商標登録=明確に識別力がある」というわけではない。
そこで、本記事では、商標の登録審査過程における「識別力」の考え方や、識別力のない商標なんぞを意見書で説き伏せてどうにか登録したところで、後から様々な不利が生じうること……について解説したい。
商標登録の主な要件:識別力と自己使用意思
商標が登録されるためには、基本的に以下のような要件が求められる。
識別力があること
商標法上、取引者や需要者が、その標章を見て「どこの会社や誰の商品・サービスなのか」を区別できる必要がある。特許庁は日常使用される一般的な言葉や単純な図形・地名などについては「識別力なし」として登録を認めない……
……のだが、実際には様々な事情があって、「こんなの全く識別力ねえだろ!」という言葉も案外あっさりと登録されてしまう。
《そもそも「識別力」とは?》
「識別力」とは、ある標章(ネーミングやロゴなど)が、その商品・サービスの提供元を他と区別しやすいか、その度合いをいう。他と区別しやすい標章は「識別力が高い」。区別しにくければ「識別力が低い」。

小久保
自動車でいうと、「プリウス」だったら少なくとも特定の車種名だと分かりますね。これが単に「ハイブリッドカー」だと、そんなモンどこの自動車会社だって扱ってるジャンル名に過ぎないので、「識別力がない」となります。
こんな風に、単なる商品やサービスの品質・用途・産地などを示すだけの表示は識別力がないとされ、反対に独創的な造語やユニークなデザインは、識別力が高いと評価される。こうした識別力の程度が、商標として保護されるか否か、ひいては登録後の権利行使のしやすさにも影響していくのだ。
自己の使用予定または使用意思があること
商標は「使用を前提とした権利」だ。将来的に自社商品やサービスに使用する目的がない場合、単なる権利の占有は許されない。

小久保
ちなみに、弁理士が二言目には口にする「商標は早い者勝ち!」ってヤツ。あれは、上記の2要件(識別力と使用意思)の要件をクリアしたあとの、さらなる関門として存在します。今回は触れないけど、そのうち触れます。
実際には約8割以上が登録される現状
特許庁が公表する統計によれば、提出された商標出願のうち8割以上が最終的に登録へとこぎつけていることがわかっている。
一見すると特許庁が審査基準をそれほど厳格に運用していないようにも見えるが、その背景にはさまざまな要因があって。
まず、弁理士や企業の知的財産担当者が出願前に「ある程度」の識別力要件を満たしやすい商標を選定すること、そして拒絶理由通知に対して意見書や補正を行うことで、最終的な登録率を引き上げる工夫がなされている点が挙げられる。
また、特許庁の審査は、明確な基準が定めづらい「識別力」の有無について、グレーゾーンに属する場合にはとりあえず登録する傾向が否定できない。
商標権には登録後にも「異議申立て」や「取消審判」、「無効審判」といった見直し手続が用意されているからだ。
つまり、特許庁は登録段階で完璧なフィルタリングを行うのではなく、後から他者が問題提起できるような仕組みを用いて、不要または不当な権利を是正する制度設計を行っているワケだ。
さらに、権利を実際に行使する段階では、侵害者に対して差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟(原則として訴訟手続)を通じて勝訴を得る必要がある。この過程では、商標権の有効性や財産的価値、権利行使の妥当性などを裁判所が改めて精査する。
このように、商標権の有効範囲や保護対象は、登録後も厳密にチェックされる仕組みになっているのである。

小久保
つまり、登録までは弁理士じゃなくてもできるぐらいカンタンだけど、権利行使段階でキッチリとその真価を問われるよって話です。
「登録=品質や価値の公的保証」ではない
ここで重要なのは、「商標登録」はあくまでも「その標章を、ある範囲・一定期間、商標権として独占的に使用できる立場を認める行為」に過ぎないことだ。登録証を得たからといって、その商標自体にビジネス的な価値やブランド力があるのだと特許庁が保証したわけではない。
むしろ、商標登録は「存在」を示すための制度であり、その「質」や「価値」を直接証明する仕組みではないのである。ブランドとしての強さ、顧客に伝わる独自性や魅力は、結局のところ市場で培われていくものだ。

小久保
もっとも、出願した自分の商標が登録されたら素直に嬉しいと思います。それは否定しないです。自分だって出願中の「namael」が取れたら1度ぐらいドヤります。
「識別力の弱い商標」は権利行使時に不利を被る
登録された後に問題となるのが、いわゆる「識別力の弱い商標」の扱い。
例えば、商品やサービスの特徴をそのまま表した記述的な標章は、たとえ登録には成功したとしても、後に他者が似たような表示を用いた場合、権利行使が困難になる。
「誰でも使いたい表現」を独占することは公正な取引秩序に反すると見なされがちだからだ。
特に、裁判では商標自体の「周知性」や「識別力」の程度が厳しく検討される。その結果、商標権者側がしばしば訴訟で敗訴したり、商標権の有効範囲を限定されたり、場合によっては「無効にすべきもの」と断じられたりするケースも。
まとめ:登録はあくまで1つの手続
商標登録は、他者の使用を排除または牽制し、自社ブランドを保護するための大切な第一歩だ。しかし、登録されたという事実それ自体が商標の識別力や信頼性を公的に担保するものではない。
「特許庁が登録を認めたから絶対的な権利性がある」などと過信せず、商標取得後もブランド戦略やマーケティング、周知活動を通じて「実質的な価値」を高めることが求められるのである。